- 東京に住む30代会社員、妻と子2人(6歳、4歳)
- 新卒入社した日系メーカーで10年強勤務。うち2015-2018年の約3年間、マーケティング担当としてアメリカに駐在。
- 現在は日本に帰任し、欧米地域のマーケティングとグローバルの事業戦略を担当。
- 趣味はブログ・資産運用 (NISAと不動産)・ガンプラ。
くらいがごく簡単な自己紹介ですが、それぞれの背景にあるストーリーを紹介します。
アメリカで情報弱者になった自分と、無いものは作ればいい精神
自己紹介に際して、本ブログの前身であるはてなブログを振り返ります。
旧へらじかブログがうまれたのは2017年夏。
アメリカ駐在3年目を迎え公私共に少しだけ落ち着いてきた頃。
気のいいアメリカ人の同僚や家庭に恵まれ、アメリカ生活でちょっと得する知恵をこれから渡米する人へ届けたかったので試しにブログを書き始めました。
自分が欲しい情報がWeb上に無い。
無いものは作ればいい。
当時の自分を想定読者として書けば、きっと誰かの役に立つ。
常に過去の自分を助けるつもりで書いていました。
・・・という動機は半分本当ですが、半分はもっとドロドロした気持ちでした。
アメリカ人経営者との仕事と、個として勝負する人への憧れ
駐在1-2年目に比べれば英語に慣れ、同僚やお客さんとコミュニケーションは取れるようになった3年目。
マーケティング担当としての仕事と同時にFP&A的な役割も担っていたため、だんだんと現地のアメリカ人経営層との接点が増えます。
彼らの言葉がわかるようになるほど言葉の面での自信はつく一方、今度はビジネスパーソンとしての格の違いに気づかされる日々。
日米ではグループ企業間であっても給与体系が全く違うので、会議で同じテーブルを囲む彼らアメリカの経営メンバーは軒並み、年収5000万円や1億円クラスということも。

このレベルのビジネスパーソンたちは仕事の面だけではなく、人格的にも素晴らしい人ばかり。
彼らと日常的に働けたことで、自分の姿勢や考え方は大きく刺激を受けました。
自分が1億円を稼げる人物になれるとはさすがに思えませんでしたが、近づきたい、スキルを盗みたいと人に思ってもらえるだけの魅力を身につけたいと。
第2言語として英語を扱う自分は、そもそも日本語で知識をつけ、能力を拡げないと、この人たちにはずっと追いつかないだろうという思いから、日本の企業家の本やインタビュー記事を読み始めました。
渡米前は、起業家の方々に対して渡米前はまったく興味がなく、いち会社員である自分と起業家とは別の世界という感覚。
「自己実現」とか、「キャリア」とか、いわゆる意識高い系のワードにも苦手意識を持っていたように思います。
ただ驚くことに、日々アメリカ人経営層と仕事をしていたことで、「個」としてのたくましさを持つ同僚たちからだんだんと企業経営・事業管理・マネジメントの視点を学習。
「意識高い系」と敬遠していた起業家の言葉を素直に受け取れるようになりました。
ここから派生して、エンジェル投資家や、日系企業の経営者などのインタビュー記事へと興味が移っていきます。
エンジェル投資家のインタビューメディアがお気に入りでした。何度も読み返してはモチベーションをもらっています。
元カルビー会長の松本氏とサイボウズ青野氏の働き方改革についての対談記事も好きでした。

いずれの方も、個人としての魅力がある人ばかり。
「個の時代」と言われ始めたいま、自分も何かを始めたいという思いがふつふつとこみ上げてきました。
マクロの人口統計×ミクロの困りごと+時間的制約=ブログ
そこから遡ること1年前、2016年に第2子がアメリカで生まれていました。
日本からアメリカまで飛行機で片道13時間という距離に加えて、諸々の事情により実家サポート無し、妻と自分の2人だけでのアメリカ出産&育児は地獄でした。
産後3週間は日米の上司に許可を得て育児休暇をもらい、その後も自宅勤務を活用していましたが、言葉の壁、文化の壁、育児ストレス、仕事もままならず・・・と家族全員が疲弊し崩壊寸前。
趣味や自分の時間はそぎ落とし、全てを家族に使う1年間。仕事のパフォーマンス評価も過去最低に。
子供たちの成長にともなって2017年にその状況が少しだけ落ち着きましたが、相変わらず日中に自由になる時間は無し。
「個の時代」に向けて何かをはじめたい。でも時間もない。
隙間時間で何かできないかと考えたのが、ブログでの情報発信。
これがピッタリとはまりました。
ガチ育児を経験された方には共感いただけるかもしれませんが、育児でつらいことの1つは大人と会話できないことです。
新生児の相手は肉体的な疲労だったり、体調変化への対応による心労が中心なのですが、社会的な生き物である人間にとって後々ボディーブローのように効いてくるのが「大人との会話の断絶」。
海外駐在という環境がそれに輪をかけて、回りに日本人がほとんどいない都市に住んでいたためにより一層精神的に閉鎖した空間に追い込まれていました。
そこに射した光が、ブログやTwitterを通じた大人とのコミュニケーション。
アメリカ生活において自分が過去に困ったこと、役立ったことを在米日本人へ情報を発信し、コメントをもらえる。
しかも育児の合間や早朝深夜にも作業が可能。
匿名の「へらじか」として、ではあるものの、個人として何かをしたいという気持ちと、時間的制約のある生活スタイルがかみ合った結果生まれたのが旧へらじかブログでした。
そしてどうやら自分の情報にはそれなりの潜在需要があり、今後もそれは増えていきそうなデータの裏づけも取れました。
ブログ記事の内容は、過去の自分が困ったこと。想定読者は常に過去の自分です。
海外在住者による旅行やグルメといった情報はありふれている一方で、お金周りのリアルな話は情報が取れず特に苦労したので、テーマの軸に据えました。
自分は中学生ごろからインターネットを使っていた世代なので、日本で生活する分には「情報弱者」になった経験はありません。
ところが一歩国外に出ると、言語の壁によって容易に「情報弱者」になり得ます。
(自分はそれでもまだマシな方で、英語の不得意な妻はより深刻)
その状況にただ困ったのが駐在1-2年目。
3年目には客観視し、逆にアドバンテージにできないかと考える心の余裕が生まれました。
一般的なマーケティング活動ではニーズ調査を行いますが、ブログを商品と仮定し、想定読者を自分と置いた場合には、ターゲットの一人である自分や妻の真のニーズをどこまでも深堀りできるので、本当にほしい情報を見つけることが可能。
「情報弱者」になってしまった自分たちを客観的に見つめて、Web検索してみて、ほしい情報がないから自分で書くことで後世に伝えていく。この繰り返しでした。
ポジティブな動機だけではなく、困りごとだったり育児のモヤモヤという負の部分も凝縮して昇華させた結果です。
ブログ開始当初はここまで考えておらず、後付けの部分も多分に含まれてはいますが。
そして、この3年間のアメリカ生活の前提になったのが言わずもがな、英語の習得でした。
純ドメ会社員が10年かかって英語を身につけた
自分の英語遍歴は、就職活動のためにTOEICを受け、大学生平均以下の420点を取ったところからスタートしています。
社会人になってぼんやりと「いつかは海外」と漠然と考える程度だったのが、外部の様々な刺激によって明確に意志を持つに至りました。
自己学習でTOEIC700点まで伸ばして、出向先から本社の海外マーケティング部門へ帰任。
帰国子女・海外MBA・駐在経験者に囲まれながらの実務、そして駐在を経てTOEICは955点に達しました。
こうして書くときれいですが、当初英語ができず帰国子女上司に詰められた話や、初の海外出張で英語通じなさすぎてホテルに帰って泣いた思い出も。
社会人10年間のTOEICスコア推移と仕事の変化については以下の記事に詳しく書いています。
英語学習のモチベーションが維持できない、周りと比べて成長が遅いと感じる人に向けて書いたので、励ましができたら嬉しいです。
手っ取り早くへらじかが使った英語勉強法や教材を知りたいという方は以下の記事へ。働きながら学習する参考になれば幸いです。
世間には、1年以下の学習で英語力が突き抜けてしまう人もいます。
残念ながら、一般人たる自分にはそれは無理でした。
もがいて、挫折して、英語を使わざるを得ない環境に自分を追い込んで、10年かかってやっとそれなりのレベルです。そんな泥臭い話にもニーズはあるのかなと、ポツポツとブログに残している次第です。
次に、本ブログのテーマの1つでもある資産運用。
これもアメリカ人同僚からの影響による部分が大きいです。
アメリカ人同僚の影響で資産運用を始めた
アメリカ人に囲まれて働く中で、仕事の面で「個」としての働き方を意識すると同時に、よき家庭人として、そして家族と一緒に描くキャリアの考え方に触れました。
日本で言うキャリアは、職歴だったりスキルだったり、働く人としてのそれに近いニュアンスだと感じます。
一方のアメリカにおけるキャリアは、ライフステージに応じて描いていく、生き方そのもののニュアンスに近い印象です。
ジョブ型の雇用に起因するのか、多様な個性によるものなのか、はたまた宗教観なのか、自分のなかでまだその違いが言語化できていません。
ただ、自分の資産を自分で作るという意識、公的年金が無いために自分で資産形成・副業をする同僚の姿勢からは、日本人にはない強さと余裕を感じました。
米国ETFと国内NISAを中心に運用
心と時間の余裕が少しだけできた駐在後期に、アメリカで得たドル建ての給与の一部を原資として米国ETFを中心に個別株も少し持っています。
金額的にはまだまだ大きくないものの、自立した生き方のために、複利の力でコツコツと資産形成をしていく予定。
帰国後は追加で、自身の一般NISAと子供2人分のジュニアNISAで高配当株を中心に運用中。
その過程を記録していくことで将来の20代、30代の資産形成の参考になれば、という思いももっています。
2020年から不動産投資スタート
2020年から日本で新たに始めたのが不動産投資。
株の延長で、資産運用として始めたのですが、実際にやってみると手間はかかるわ知識は要るわで一つの事業であり経営なんだなというのを身にしみて実感しています。
2020年春に中古の1棟アパートを購入し、今のところ順調に経営中。その道のりやリアルな収支をTwitter上では #へらじか不動産 とタグ付けして呟いたり、ブログでも綴っています。
こちらの記事では学習から購入までをステップごとに解説しています。会社員かつ不動産に興味がある方向け。
そしてこちらは、丸1年経営した上での収支を書いています。
家賃収入480万円、手残りキャッシュフロー140万円という結果でしたが、出来過ぎなので、今後浮き沈みはあると思います。
そして将来に向けた思いとしてもう一つ大事にしたいのが、子供への英語教育。
子供の英語教育に超長期で取り組む
上記の考え方・視野の広がりは英語を通じて身につけたものです。
英訳・和訳のスキルという語学単品の話ではなく、英語を通じて価値観を取り入れて生きてほしい。
まして子供たちが社会に出る2040年にはいまよりもっとグローバルな世の中なのだから。
などと親は勝手に考えていますが、結局のところどう生きるかは子供たち次第なので、環境を与えてみて15年くらい様子をウォッチしたいなと。
こうした思いから、子供2人の英語学習のトライ&エラーをブログに綴ります。
小学校での英語教育が必修化される中で、情報の需要はあるはず。
ただ、わが子をサンプルにすると何かを試しても結果が出るまで年単位の時間がかかる点は、もしかするとブログネタとしては不適かもしれません。
このテーマは焦らず超長期でのんびりと見守っていこうと思います。
以上、自己紹介やいま考えていることと、将来の展望でした。
考えに変化があればまた、書き換えます。
2018年12月1日 初版
2021年4月30 日 第3版






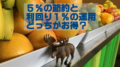
コメント
ただいまアメリカ駐在中で来月帰国します.
へらじかさんのブログを参考にアメリカ発行のクレジットカードを作成しようと思っています(FICO 740台).
帰国後も続けて使えるようなオススメのカードはありますでしょうか?
へらじかさんが帰国後も持っているアメリカ発行のクレジットカードがあればご教授いただきたいです.
また,帰国後アメリカ発行のクレジットカードを保持する際,登録住所や,カード切り替えの際の手続きなどはどうなるのかも知りたいです.
宜しくお願い致します.